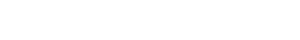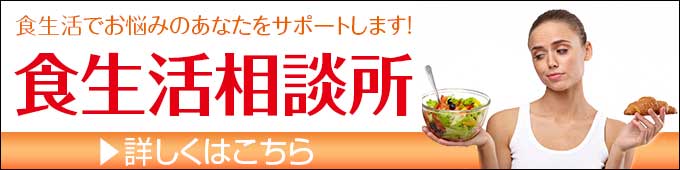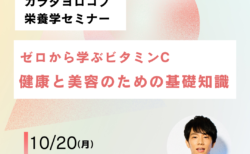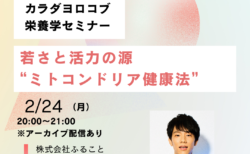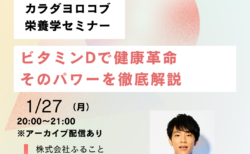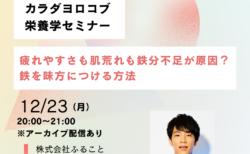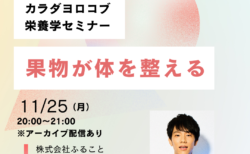週末の午前中に作れる ぬか床の作り方を写真つきで紹介
こんにちは。
管理栄養士の圓尾(まるお)です。

自宅でぬか漬けを漬ける習慣、
はじめてみませんか?
漬け物には植物性の乳酸菌がたっぷり。
腸内環境を整え、健康と美容に役立ちます。
しかし悲しいかな、
市販されている出来合いの漬け物は
ほとんどが十分発酵されずに
食品添加物のオンパレードです。
かくなる上は……
そう、自分で作っちゃえばいいのです。
ぬか漬けなら、最初にぬか床だけ作って
野菜などの漬け材料があれば
いくらでもぬか漬けを作ることができ、
ぬか床は半永久的に使えます。
「でも、ぬか床を作るのって難しそう……」
いえ、そんなことはありません。
最初にかかる時間は30分もいりません。
後は生き物を育てる感覚で
毎日一分お世話をするだけでオーケー。
今回はそんなぬか床の作り方をご紹介します。
※ 初めての著書『一日の終わりに地味だけど「ほっとする」食べ方』好評発売中!!
週末の午前中に作れる ぬか床の作り方を写真つきで紹介
準備するもの
容器
ぬか床を入れる容器はいざという時に
冷蔵庫に避難させやすい
ホーローがオススメ。

僕は野田琺瑯さんの容器を愛用しています。
見た目もこざっぱりとして洒落ています。
この大きさでぬか1キロ分のぬか床が作れます。
四人家族でも一日分が漬けられる量です。
ぬか 1kg
玄米を白米に精米する過程で出るぬかには、
生の「生ぬか」と炒った「炒りぬか」があります。
僕は生ぬかを使いました。

ぬかは農薬が残留しやすい部位なので、
意地でも有機・無農薬のものを選びましょう。
塩 110g
こちらは精製塩ではなく、ミネラルも入った自然塩を。

「海の精」は手に入りやすいです。
昆布、唐辛子

昆布はうま味を加えてくれ、
唐辛子は防腐作用があります。
昆布は5cmの長さのものが二枚、
唐辛子は二本を手でちぎって中の種は除いておきましょう。
水 800cc〜1000cc
ぬか床の様子を見ながら加えていきます。
水道水ではなく、ミネラルウォーターを。
ぬか床づくり手順
さあ、材料が揃ったらいよいよ作っていきます。
作業時間はだいたい30分を見ておけば良いでしょう。

1、ボウル、または鍋に塩とぬかを加えます。

2、よく混ぜてから、水を三回ぐらいに分けて加えます。
一回加えるごとに全体を混ぜます。

3、よ〜く混ぜ合わせ、味噌くらいの固さになるように水分量を調整します。

できたら容器にお引っ越し。

4、昆布と唐辛子を入れて中に入れ込みます。

5、全体を平らにしたら出来上がり!
捨て漬けの手順
ぬか床ができて
早速野菜を漬けていきたいところなのですが、
まだぬか床が完成したわけではありません。
ぬか床に乳酸菌を入れてやらねばなりません。
このために、「捨て漬け」ということをします。
これはいらない野菜を漬けて、
そこについている乳酸菌を
ぬか床の中に繁殖させるという行為。
キャベツの一番外側の葉っぱや
大根やにんじんのヘタの切れ端なんかを漬けていきます。

今回はキャベツを使いました。

混ぜ込んだら、また表面を平らにならしましょう。
この後ですが、
一日一回は底から全体をかき混ぜ、
3〜4日したら捨て漬けした野菜を取り除き、
新たな捨て漬け用の野菜を加えます。
これを3〜4回ほど繰り返して
全体が少し酸っぱいような香りがしてきたら
いよいよ本野菜を漬けてデビューできますよ。

まとめ
ぬか床はできたばかりのときから
いきなり美味しいぬか漬けが
できるわけじゃなかったりします。
少しずつ、いろんな野菜を漬けていくと
どんどん美味しく育っていく。
以前、居酒屋のランチで食べたぬか漬けが
ビックリするほど美味しく、
お店のおばちゃんに聞いてみたら
自家製のぬか床で漬けており、
なんとそのぬか床が
50年物とのことでした。
長い年月が刻まれたぬか床で漬けられたぬか漬けは
決して機械や添加物では作り出せない味わいがあります。
自分のぬか床が将来
子どもに受け継がれる。
なんてのを想像するのも楽しいですね。
さあ、ぬか床とともに生きる生活をはじめましょう!
【参考】「ぬか漬けの基本 はじめる、続ける」山田奈美 グラフィック社
※ 初めての著書『一日の終わりに地味だけど「ほっとする」食べ方』好評発売中!!